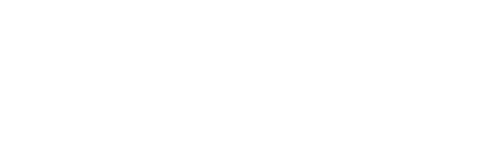今年の萩市のトップアイコンは、なんといっても、世界遺産登録10周年です!

萩に世界遺産?どこに?いくつ?あれ、そもそも萩ってどこだっけ?
萩市が誇る世界遺産をめぐりながら、開運&パワーチャージする、
とっておきの「#萩旅」をご紹介します!
目 次
▼ 世界遺産めぐりを始める前に、「萩・明倫学舎」で楽しく学ぼう!
▼ ①『萩城下町』
▼ ②『萩反射炉』
▼ ③『恵美須ヶ鼻造船所跡』
▼ ④『松下村塾』
▼ ⑤『大板山たたら製鉄遺跡』
▼ マンガで萩の世界遺産について紹介しています
2015年7月、萩市は、山口県内初の「世界遺産登録」に湧きました。
『明治日本の産業革命遺産 ~製鉄・製鋼、造船、石炭産業~』
「明治日本の産業革命遺産」は、幕末から明治末までの日本の産業化の過程を示す産業遺産群のこと。
北は岩手から、南は鹿児島まで、8県11市の広域にわたる資産を1つのテーマのもとに束ねて世界遺産に登録する手法(シリアルノミネーション)で、23の構成資産が世界遺産に登録されたのです。
うち、萩エリアは、時代順に1番目のエリアで、「萩城下町」、「萩反射炉」、「恵美須ヶ鼻造船所跡」、「松下村塾」、「大板山たたら製鉄遺跡」の5つの資産があります。
その他、昨年(2024年)のテレビドラマで話題になった炭鉱の島「端島炭坑(長崎県)」をはじめ、「官営八幡製鐵所(福岡県)」、「韮山反射炉(静岡県)」などで構成されています。
日本は、幕末における西洋技術の導入以来、西欧以外の地域で初めて、かつ極めて短期間のうちに飛躍的な発展を遂げ、明治時代後期には産業国家としての地位を確立しました。
このことは、経済大国となった日本の礎になるとともに、世界的な価値を持っています。
「明治日本の産業革命遺産」について、詳しくは、こちら
👣
さぁ、萩で世界遺産めぐりを始めるなら、
まずは「萩・明倫学舎(はぎ・めいりんがくしゃ)」へ向かいましょう。

全国屈指の規模を誇った、藩校明倫館の跡地に建ち、
平成26年3月まで授業が行われていた旧明倫小学校校舎が、3年の改修整備を経て、萩の観光起点「萩・明倫学舎」に生まれ変わりました。


▲あたたかみのある館内は、フォトスポットがたくさん!
およそ90mの廊下を有する長~い校舎は、4棟が整然と並び、迫力満点。
赤い瓦と、黒と白のツートンカラーの外壁が目を引く、レトロな建築物です。

正面にある本館から数えて2棟目となる、2号館は、「世界遺産ビジターセンター」となっており、萩にある5資産についての位置づけや詳細、近代化を成し遂げる上でどのような役割を果たしたのかなど、映像やパネルで分かりやすく解説しています。
ここを見てから現地へ行くと、より世界遺産めぐりが楽しめます✨


「長州ファイブ」をご存じですか?
開国をするか、攘夷(海外の勢力を打ち払って入国させないこと)を実行するべきか、混乱の渦中にあった幕末期の日本。海外渡航が禁止されていた時代ですが、1863年、攘夷に傾く萩(長州)藩は、欧米に打ち勝つための技術・知識を学ぶため、5人の藩士を密かに英国へと送り出しました。
長州藩の、ひいては日本の未来を託されたのは、なんと20代の若者たち!
命からがら辿り着いた英国の地で目にしたのは、港にひしめく蒸気船や立ち並ぶビル。日本との圧倒的な国力差を肌で感じた5人は攘夷は不可能と悟り、欧米の近代文明を積極的に学びました。
彼らの名は、伊藤博文、井上馨、山尾庸三、遠藤謹助、井上勝。
帰国後、政治や鉄道、造幣などそれぞれの分野で活躍し、日本の近代化・工業化の礎を築きました。近年、彼らの評価が高まり、「長州ファイブ」という呼称で知られています。
萩・明倫学舎には、レストランやお土産ショップ、喫茶も併設されています。


では、実物を見に行きましょう!
まずは、『萩城下町(はぎじょうかまち)』。

1600年、関ヶ原の合戦後、毛利輝元により、萩城が築城され、萩城下町として、およそ260年間、萩を本藩として、萩(長州)藩の政治・行政・経済の中心として栄えました。
江戸時代は、士農工商の身分制度が確立されており、萩城下町も武士と町民の暮らす区画は厳格に区別されていました。資産の範囲は、城跡、旧上級武家地、旧町人地の3地区です。
●城跡 萩城跡指月公園

●旧上級武家地 堀内鍵曲

●旧町人地 江戸屋横町

まるでタイムスリップしたみたい!
🍊
城下町のたたずまい(武家屋敷周囲の壁土塀・長屋門など)が、今日まで維持された背景には、萩を象徴する “ある果実” の存在があります。
その果実とは、


「夏みかん」のこと!
明治維新後、生活の術を失った士族たちを救うため、空き地となった武家屋敷で始まった、夏みかんの集団栽培。
風の強い場所が苦手な夏みかんにとって、屋敷を囲う強固な土塀は、風よけにピッタリ。
つまり、城下町らしい景観が維持されているのは、夏みかん栽培が現在まで受け継がれてことで、武家屋敷の敷地割が変わっていないからなのです。
。
★ここで「開運グルメ」!★
夏みかんは、前年になった実を収穫しないでおくと、同じ木に前年の実と今年の実がなった状態になります。果実が何年も木になり続ける、その様子から代々続くという意味で「夏代々(なつだいだい)」とも呼ばれる縁起物です。
晩秋から、黄色く色づく夏みかんですが、酸味が強くてまだまだ食べられません。木の上で冬を越してじっくり熟成してから収穫するため、旬は5月~6月。
甘酸っぱい果実をそのまま食べることは叶いませんが、萩城下町には、夏みかんを使った、ソフトクリームやわらび餅、ぷりんなどの食べ歩きグルメがあります。


。
つづいて、『萩反射炉(はぎはんしゃろ)』をご紹介します。

反射炉とは、西洋で開発された金属溶解炉のこと。
江戸時代末期、萩藩は外国からの脅威に備え軍事力の強化をはかるために反射炉の導入を試みました。(当時は鉄製大砲を鋳造するには、衝撃に弱い硬い鉄を粘り気のある軟らかい鉄に熔解する必要があり、その装置として反射炉が用いられていました。)
安政2年(1855)、反射炉の操業に成功していた佐賀藩に藩士を派遣し、鉄製大砲鋳造法の伝授を申し入れますが、拒絶され、反射炉のスケッチのみを許されます。このスケッチをもとに萩反射炉を建設しました。
萩藩の記録で確認できるのは、安政3年(1856)の一時期に試験的に操業され金属の溶解実験が行われたということだけであることから、萩反射炉は試作的に築造されたと考えられています。西洋の科学技術への試行錯誤を象徴している遺構です。
現在、煙突にあたる部分(高さ10.5m)が残っています。
春には、反射炉の後ろから桜が咲き、萩の桜の名所となっています。

。
萩反射炉から、徒歩でおよそ10分。
『恵美須ヶ鼻造船所跡(えびすがはなぞうせんじょあと)』にやって来ました。

嘉永6年(1853)、幕府は各藩の軍備・海防力の強化を目的に大船建造を解禁し、のちに萩藩に対しても大船の建造を要請しました。
恵美須ヶ鼻造船所跡は、萩藩が安政3年(1856)に設けた造船所の遺跡で、幕末に萩藩最初の洋式軍艦「丙辰丸(へいしんまる)」(ロシア式の技術)、「庚申丸(こうしんまる)」(オランダ式の技術)という2隻の西洋式帆船を建造しました。
ロシアとオランダという2つの異なる技術による造船を1つの造船所で行った例は他にないこと、また幕末に建設された帆船の造船所で唯一遺構が確認できる造船所であることが評価されています。
。
つづいて、『松下村塾(しょうかそんじゅく)』。
明治維新の先覚者・吉田松陰(よしだしょういん)が主宰した私塾です。

幕末動乱の時代に生を受け、「至誠」を貫き通し勇敢に行動した吉田松陰。
直接自分の目で海外の実情を確かめたいと考え、下田(静岡県)でペリーの黒船へ向かい、密航を企てようと試みるも、失敗。野山獄に投獄の後、実家である旧松本村の杉家に幽囚の身となりました。ここで親類や近所の若者に講義をはじめ、のちに松下村塾を主宰し、身分や階級にとらわれず指導に当たることになりました。
松陰は、海防の観点から工学教育の重要性をいち早く提唱し、工学の教育施設を設立し在来の技術者を総動員して自力で産業近代化の実現を図ろうと説きました。その教えを受け継いだ塾生らの多くが、後の日本の近代化・産業化の過程で重要な役割を担いました。
松下村塾は、木造瓦葺き平屋建ての建物がそのまま残り、松陰が幽閉された幽囚室のある実家とともに世界遺産の構成資産の一つとなっています。

▲塾生たちの声や足音が聞こえてきそう!
。
★「開運スポット」!松陰神社 ★
吉田松陰を祭神とする神社です。
学問の神として信仰が厚く、境内には、松下村塾をはじめ松陰ゆかりの史跡が点在しています。
おみくじには、松陰先生のことば(御教訓)が入っています。


。
最後は、『大板山たたら製鉄遺跡(おおいたやまたたらせいてついせき)』

萩市街地から車でおよそ40分の福栄地域にある、大板山たたら製鉄遺跡。
砂鉄を原料に、木炭を燃焼させて鉄を作っていた江戸時代のたたら製鉄の跡です。
この地が選ばれたのは、周りに炭の原料となる豊富な山林があったから。
日本の伝統的な製鉄方法で、1750年代~1860年代の間に3回操業していました。
恵美須ヶ鼻造船所で建造した1隻目の西洋式帆船「丙辰丸」を建造する際に、大板山たたらで製鉄されたものが船釘などに利用されたことが、古文書で確認できたことが、世界遺産登録の理由となりました。
。
★「開運土産」!萩の焼き抜き蒲鉾 ★
遠火で板の底からじっくり時間をかけて炙り焼く、焼き抜き製法が特徴です。
独特のプリプリとした弾力のある食感は、これまでの蒲鉾の常識を覆します!
かまぼこの丸みのある断面は、日の出を表しており、日の出のかたちに似たかまぼこは縁起物として広く親しまれています。


▲蒲鉾のニュースタイル「 蒲鉾バーガー」もおすすめ!
VR技術を使って、萩市に存在した世界遺産の風景を眺めることができます!

萩城跡指月公園では、「萩城」の天守を。
恵美須ヶ鼻造船所跡では、「丙辰丸」や「庚申丸」の姿や造船所の建物の様子が再現されています。
お手持ちのスマートフォンやタブレットを利用してご覧ください!
詳しくは、こちら
👣
いかがだったでしょうか?
先人たちが、外国に負けない国を築こうと試行錯誤した姿に触れることができます。
その情熱と努力から、きっとパワーをもらえるはず。
世界遺産10周年を機に、「明治日本の産業革命遺産」をめぐりませんか?
**********
マンガで萩の世界遺産について紹介しています!
「マンガでわかる!萩の世界遺産」は、第1話から第7話までの全7話で構成されています。
このマンガでは、桂小五郎(木戸孝允)がナビゲーターとなって、萩の世界遺産と長州ファイブについてご紹介します。
イラストでとてもわかりやすいので、ぜひこちらもご覧ください!
↓ 下のバナーをクリックしてください